近年、「戸籍不要論」に関する議論がSNSやニュースで活発に取り上げられています。相続や婚姻などで必要な戸籍制度ですが、その煩雑さや時代に合わない仕組みに疑問を持つ声が増えています。なぜ今、戸籍制度を「廃止したい」と考える人が多いのでしょうか。
「戸籍制度を廃止するとどうなる?」
この疑問を解消することで、暮らしや行政手続きへの理解にもつながります。
また、戸籍制度が残る国は「日本だけ」とされ、海外では個人単位の登録制度が一般的です。特に「外国人」への対応には課題が多く、国際的な制度との違いを知ることも重要です。
- 戸籍制度が不要とされる主な理由
- 戸籍制度を廃止した場合の影響
- 日本が戸籍制度を維持する背景
- 他国との制度比較や国際的な流れ
戸籍不要論が注目される背景とは
- 戸籍制度を廃止したいのはなぜか
- 廃止するとどうなるか
- なぜ日本だけに残るのか
- 戸籍がマイナンバーと重複している問題
- 戸籍制度は縦割り行政の象徴なのか
戸籍制度を廃止したいのはなぜか
戸籍制度を廃止したいと考える理由には、主に手続きの煩雑さと時代に合わない制度設計が挙げられます。現代社会では、個人を識別・管理するための手段としてマイナンバー制度が導入されており、戸籍制度と役割が重複していると感じる人が増えています。
実際、相続や婚姻といった人生の重要な場面では、戸籍謄本の取得が必須です。しかしこれには多くの時間と費用がかかり、複数の自治体をまたいで取り寄せなければならないケースもあります。例えば、相続人を特定するために亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍を集める必要があり、高齢者やデジタルに不慣れな人には大きな負担となります。
さらに、戸籍制度には家制度の名残があり、家族単位での管理が前提となっています。この仕組みが、女性の改姓強制や夫婦同姓の義務といった個人の選択を制限する要因にもなっているのです。そのため、個人主義や多様性を尊重する現代の価値観と整合しないという批判が高まっています。
このように、制度の非効率さと社会的な価値観の変化が、戸籍制度の廃止を求める声を後押ししています。

筆者は、まだ戸籍が必要と考えているよ。身分や家族関係を公的に証明できる戸籍の存在は、トラブル防止や社会秩序の維持に不可欠だよね。
廃止するとどうなるか
戸籍制度を廃止した場合、家族単位での身分関係を証明する手段がなくなり、個人単位の情報管理への大きな移行が必要になります。これは行政手続きの簡素化につながる可能性がありますが、同時にいくつかの新たな課題も生じます。
例えば、戸籍は相続人の確認や遺産分割協議の際に欠かせない資料です。これがなくなると、相続人を特定するために、裁判所による認定手続きなど、より複雑で時間がかかるプロセスが必要になる恐れがあります。また、婚姻や離婚の記録、公的証明書の発行手続きにも大きな変更が求められます。
一方で、住民票やマイナンバー制度を拡張することで、戸籍の代替として機能させることも考えられます。例えば、外国では社会保障番号や個人登録番号によって個人を管理する国が多く、こうした制度への転換が現実的な選択肢になるでしょう。
このように、戸籍制度の廃止は行政の仕組みそのものに大きな再設計を迫るものであり、利便性と引き換えに新たな制度的整備が必要になる点は無視できません。

戸籍があるからこそ相続や婚姻時に正確な確認ができるとし、廃止はかえって混乱を招くと考えられるよ。
なぜ日本だけに残るのか
戸籍制度が日本にだけ残っている主な理由は、長い歴史的背景と、家族を基礎とした国家運営の思想が根強く残っているためです。古代の律令制度から始まった戸籍は、身分や徴税、兵役管理のために発展し、明治以降は「家制度」と強く結びつく形で制度化されました。
現在では、台湾を除き、戸籍制度を維持している国はほとんどありません。韓国も2008年に廃止し、個人単位の住民登録制度に切り替えています。中国は本籍と居住地を分けた戸口制度を整備し、デジタル化により効率的な個人管理を実現しました。
日本では、法務省や総務省、デジタル庁といった縦割りの行政構造が、制度の統合や見直しを難しくしている要因の一つです。さらに、戸籍を「家族の絆」や「文化的アイデンティティ」として評価する声もあり、これが制度維持の根拠とされることもあります。
こうした複数の要素が重なり合い、日本がいまだに戸籍制度を保持する数少ない国となっているのです。
戸籍がマイナンバーと重複している問題
戸籍とマイナンバーは、どちらも国民の情報を管理する制度ですが、機能や運用が重複している点が問題視されています。特に「身分確認」や「個人識別」という役割において、両制度の境界が曖昧であることが混乱を招いています。
例えば、マイナンバーは税や社会保障、災害対策などを目的とした個人番号制度であり、すでに多くの行政サービスに紐づけられています。それにもかかわらず、相続や婚姻の手続きでは戸籍の提出が求められます。これは、同じような本人確認を二重に求められている状態ともいえます。
さらに、マイナンバーの担当はデジタル庁、戸籍は法務省、住民票は総務省と、それぞれ異なる省庁が所管しており、情報の一元化が進んでいないことが混乱の根本にあります。たとえば、結婚の際に改姓した女性が職場や金融機関などで旧姓使用を希望しても、戸籍とマイナンバーの情報が連携していないため、手続きが煩雑になることがあります。
このように、マイナンバーと戸籍が別々に管理されている現状は、国民にとって非効率で負担の大きい制度となっているのです。

一方で、マイナンバーではカバーできない親族関係の記録を保持する仕組みとして戸籍が必要だね。
戸籍制度は縦割り行政の象徴なのか
戸籍制度は、まさに日本の縦割り行政の象徴とも言える存在です。制度そのものが、複数の省庁によって分断的に運用されており、効率的な情報共有や制度改革が妨げられています。
具体的には、戸籍は法務省、住民票は総務省、マイナンバーはデジタル庁がそれぞれ担当しています。このような体制では、たとえば住所変更や氏名変更があった場合に、複数の役所で個別に手続きを行わなければならず、当事者の手間が増える一因となっています。
さらに、各制度が連携していないため、行政内部でも情報の突き合わせに時間がかかるという課題があります。これは、被災地などで迅速な対応が必要な場面でも大きな障害になります。たとえば、震災後の身元確認や相続処理の際に、戸籍の取得に時間を要して手続きが滞ることがありました。
これらの背景から、戸籍制度は単なる身分登録の枠を超えて、旧来型の行政運営の非効率性を象徴する存在となっているのです。
戸籍不要論の課題と論点を整理する
- 相続手続に与える影響
- 戸籍制度の歴史的背景と変遷
- 戸籍制度が外国人に与える不利益
- 世界の中で見た戸籍制度の特殊性
- 差別を助長しているのか
相続手続に与える影響
戸籍制度は、相続手続きにおいて相続人を特定するための基本資料となっており、現行制度では不可欠な存在です。相続が発生した場合、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要があります。これは誰が正式な相続人であるかを確定するための根拠となるからです。
たとえば、被相続人が複数回の婚姻や離婚を経験していた場合、以前の戸籍にも子どもの記載がある可能性があり、それを見逃すと法的な相続権のある人物が抜けてしまう危険があります。そのため、金融機関や法務局では一連の戸籍の提出が義務付けられているのです。
一方で、戸籍の取得には手間と費用がかかり、特に本籍地が遠方にある場合は郵送での請求や平日の窓口訪問が必要になります。さらに、旧字体や難解な表記が含まれることもあり、読み解くこと自体が困難という声もあります。
このように、戸籍制度は相続人の確定において重要な役割を果たしている一方で、煩雑さや非効率さが大きな課題となっているのが現状です。
戸籍制度の歴史的背景と変遷
戸籍制度は、日本で古くから続く人の登録制度であり、支配や税の徴収、兵役管理などを目的として発展してきました。最初の全国的な戸籍制度は、670年の庚午年籍にさかのぼり、飛鳥時代の律令体制下で整備されたものです。
その後、平安時代には制度が形骸化し、江戸時代には「宗門人別改帳」や「過去帳」などが代替的な役割を担いました。現在の戸籍制度の原型は、明治時代の「壬申戸籍」に始まり、国家が国民を家族単位で把握・管理する体制が築かれました。
戦前の戸籍は「家制度」の考え方が中心で、戸主に強い権限が集中していたため、個人の自由が制限される場面も多く見られました。戦後は憲法のもとで家制度が廃止され、現在の「夫婦と子を基本単位とする戸籍」へと改められています。
このように戸籍制度は、時代ごとの統治体制や社会的価値観の変化を反映しながら形を変えてきました。制度が持つ歴史の重みと同時に、現代の社会構造に適応できているかが今後の重要な論点となります。
戸籍制度が外国人に与える不利益
日本の戸籍制度は、日本国籍を持つ人だけを登録対象としており、外国人はその枠組みに含まれません。そのため、外国人にとっては不利益を感じる場面が少なくありません。特に日本人と結婚した外国人配偶者にとっては、家族関係の証明が難しくなるケースがあります。
たとえば、外国人の夫と日本人の妻が結婚しても、戸籍には夫の名前が記載されるものの、筆頭者にはなれず、日本式の表記で不自然な構成になってしまいます。このことが、役所や金融機関での手続きの際に混乱を生むこともあります。
また、国際的な家族関係が増える中で、子どもが日本国籍を持っていない場合、戸籍に記載されず、親子関係の証明が煩雑になるケースもあります。加えて、日本で長年生活していても、戸籍に名前が載らないことで社会的な“見えにくさ”を抱える外国人も少なくありません。
このように、外国人にとって戸籍制度は、自身の家族関係や身分を十分に反映できないという面で、制度上の壁となっています。多様化する家族の形に制度が追いついていないという現実が浮き彫りになっています。

制度の改善で外国人対応の柔軟性を高められる余地があり、廃止ではなく修正を求めるべきだね。
世界の中で見た戸籍制度の特殊性
日本の戸籍制度は、世界的に見ても非常に特殊な制度とされています。その理由は、家族単位での身分登録を国が公的に管理している点にあります。多くの国では、個人を単位とした識別制度が採用されており、家族構成を公的台帳で管理する仕組みは存在しません。
例えば、アメリカでは社会保障番号(SSN)が公的識別の基盤となっており、家族構成の情報を国が一括して管理することはありません。フランスやドイツなど欧州諸国でも、戸籍に該当する制度は廃止され、個人ごとに生涯IDのようなものを使って行政サービスを受ける形になっています。
これに対し、日本は戸籍に「筆頭者」を設け、夫婦や子どもを同じ戸籍にまとめて記録する仕組みを維持しています。このことが、婚姻や相続、国籍の取得・喪失などあらゆる場面に影響を及ぼしており、生活の中で戸籍を求められるケースが他国と比べて非常に多くなっています。
このように見ていくと、日本の戸籍制度は、国際的な個人識別の流れから大きく離れた、いわば「家族単位による管理」という過去の制度を色濃く残した存在だと言えるでしょう。
差別を助長しているのか
戸籍制度は、特定の社会的立場や出自を可視化してしまうことで、差別の温床になる恐れがあると指摘されています。特に問題視されてきたのが、婚外子や無戸籍者に対する扱いです。
現在の戸籍には、出生届を出す際に「嫡出子(婚姻中に生まれた子)」か「非嫡出子(婚姻外の子)」かを記載する欄があり、これが本人の意思とは無関係に法的な区別を生み出してしまいます。表面上、相続権などの差別は法律上廃止されたものの、戸籍上の記載が残ることで社会的な偏見を助長する要素になりかねません。
また、女性の再婚禁止期間や、夫婦同姓の強制といった規定も、個人の選択を制限し、特に女性に不利益が及びやすい制度構造となっています。例えば、結婚に際して96%以上のケースで女性が改姓しており、仕事や生活で不便を感じる人も少なくありません。
さらに、部落差別や被差別部落出身者の特定に戸籍が悪用された過去もあります。このような背景から、戸籍制度そのものが差別的な構造を内包しているのではないかという批判が続いています。
こうした状況を踏まえ、多くの人権団体や国際機関が日本に対して制度の見直しを勧告しているのです。差別を生まない社会を目指すのであれば、戸籍制度の再構築が避けられない課題といえるでしょう。

差別の問題は制度の使い方の問題であり、本来の機能とは切り離して考えるべきかな。
戸籍不要論をめぐる主な論点とその全体像
- 戸籍制度は手続きが煩雑で時代に合わない
- マイナンバー制度と役割が重なり非効率
- 相続や婚姻のたびに戸籍謄本の取得が必要
- 高齢者やITに不慣れな人にとって大きな負担
- 家制度の名残が個人の選択を制限している
- 戸籍廃止には行政制度の大幅な再構築が必要
- 廃止後は相続人確認がより複雑になる懸念
- 多くの国が戸籍制度をすでに廃止している
- 日本では行政の縦割りが制度維持の障壁
- 結婚や離婚時の記録手続きに戸籍が依存している
- 外国人配偶者は戸籍に完全に反映されない
- 無戸籍者や婚外子への差別が温存される恐れ
- 過去に戸籍が部落差別に利用された歴史がある
- マイナンバーと戸籍情報が連携しておらず煩雑
- 戸籍制度は国際的に見ても極めて特殊な制度
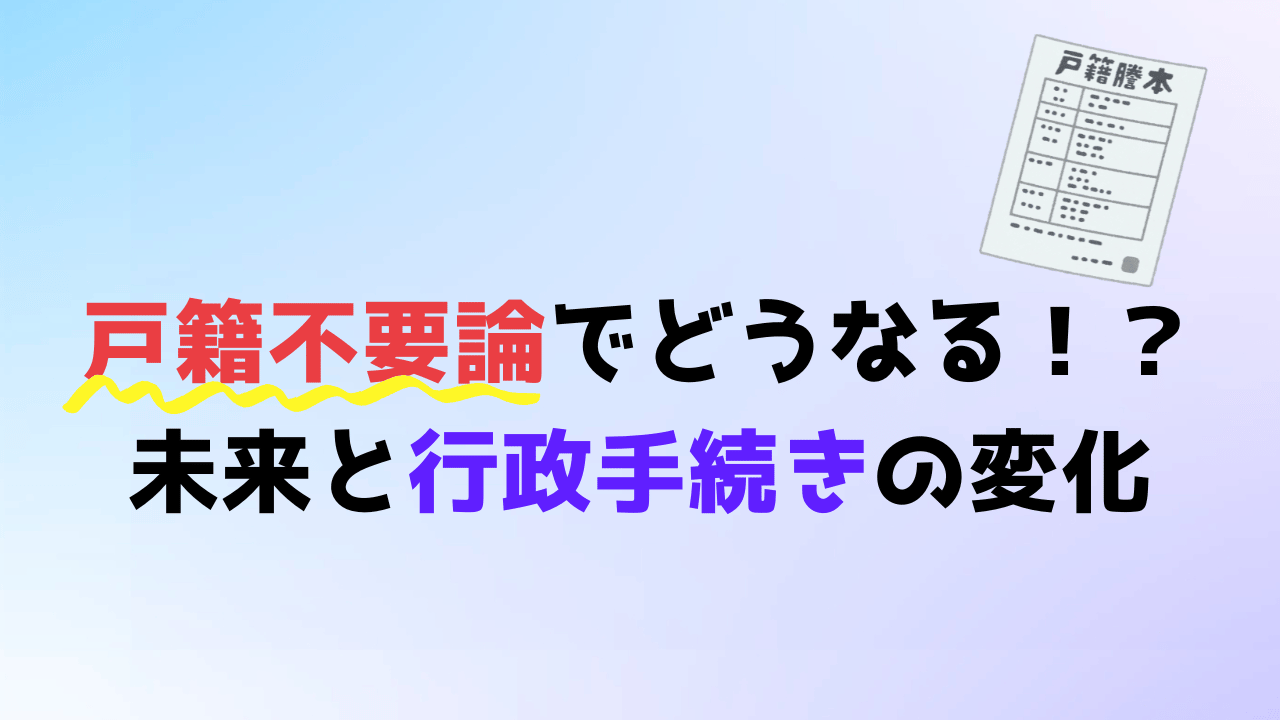
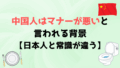
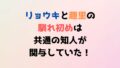
コメント